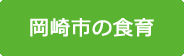給食ができるまで
給食が毎日どうやってできているのか紹介します
出勤したら一番にすることは健康チェックです。
今日の体温、自分や家族の体調に問題がないこと、手に傷はないかなど、給食が安全に調理できることを確認し記録します。
調理場に入る前に、専用の調理着に着替えます。
頭には髪の毛が入らないようにネットをかぶった上に帽子をかぶります。調理着には、中に着ている服からほこりや繊維が落ちないような工夫がされています。また、給食に入ってしまうおそれがあるため、ボタンはついていません。
着替え中にゴミや髪の毛が調理着についてしまう可能性もあるので、粘着テープをかけます。

調理場に入る前には、必ず手を洗います。 流水で手を洗った後、石鹸をつけて手のひら、手の甲、指の間、親指の付け根、指先、手首、肘までを洗います。 石鹸を流した後、もう一度同じように洗い、爪ブラシで爪の間を洗い、水で流します。
ペーパータオルでしっかり水気を取ったあと、アルコールをすりこみます。


発注した食材を受け取り、チェックをすることを検収といいます。
まず、納品された食材の数量が正しいか確認します。

次に注文通りの商品か、新鮮か、正しい温度かなど品質をチェックし、記録します。

加工食品の納品時には、原材料を確認します。アレルギー事故を防ぐため、発注した加工品の材料が事前に聞いているものと異なっていないか確認しています。
納品された食材は、保存食を採取します。保存食とは、食中毒やその疑いが発生した際に、発生原因の調査のために保存しておくものです。50グラム以上取り、2週間保存します。
納品された食品は、皮むき、洗浄などの下処理をします。
じゃがいも、玉ねぎなどの根菜は、皮むき機を使って皮をむきます。機械だけではむききれない部分もあるため、人の目でチェックし、むき残しがないようにします。

生野菜は3回洗います。そのためシンクは1回目、2回目、3回目の3つに分かれています。
汚れを残さないよう、ねぎのわかれている部分も一本ずつ丁寧に洗います。


グリンピースやコーンなどの冷凍野菜は、さやや芯、傷んだ粒が入っていないかチェックします。

下処理が済んだ食材は、フードスライサーを使用して切裁します。
フードスライサーを使用するときには、1つの釜に入る量を切るごとにねじのゆるみや刃こぼれ、異常音がないか確認をして記録します。


≪調理釜≫
蒸気で熱くなるお釜を使用して煮物や炒めものなどの調理を行います。
1つのお釜で小学生で約1000人分、中学生で約800人分作ることができます。
全ての料理は、加熱した際に90℃以上あるか確認し、記録します。
90℃以上に加熱することによって食中毒菌やノロウイルスなどをやっつけることができます。
○煮る

○炒める


≪和え物≫
材料を釜で茹で、温度が90℃以上あるか確認し記録します。


真空冷却器で10℃以下に冷却します。

和え物専用のお釜で調味料と和えます。

≪揚げ物≫
揚げ物は、ベルトコンベアに並べるとフライヤーに投入されます。フライヤーの油の中を通り、揚がったものが出口に出てきます。
出てきたものは、温度が90℃以上になっているか確認し、記録します。


完成した給食をクラスの人数分になるように食缶やフライバットに入れることを配缶といいます。
クラスと人数を読み上げて確認しながら、作業を行います。


コンテナに積み込み、配送車で学校へ届けます。



各種検査の実施
安心、安全な給食を作るために、定期的に施設の衛生管理検査、納品された食材の検査、調理器具の拭き取り検査を行っています。